
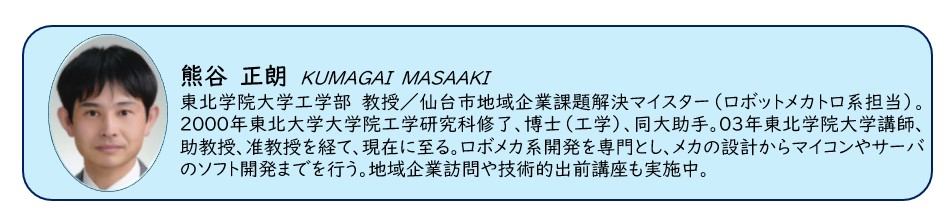
オープンキャンパスの模擬講義
初夏から夏にかけて、大学はオープンキャンパスシーズンです。一般受験はしばらく先の話ですが、学校推薦型や総合選抜(AOという呼び方も)などはこれから出願時期を迎え、高校内の選抜や、大学側の選考が一部始まります。それゆえ、それらを検討する高校3年生、受験生さんたちは、最終的な進路目標を決断するための情報収集、あるいは、自分の志望動機を再確認するためなどで来場します。7月末には1、2年生の率が高まりますが、1年後2年後を見据えての参加とともに、キャリア教育の一環として1、2校のオープンキャンパス見学を夏休みの宿題としている高校もあるようです。
私はロボット分野ということもあって、このような場面ではしばしば模擬講義を担当します。毎回2回ずつ、「ロボットをつくる」というタイトルで話していたのですが、今回、ちょっとした出来心で、1回は従来通り、1回は「オルガンを知る」という全く別ネタでやることにしました。
少し前の回もオルガン(パイプオルガンのこと)の話を書いていたように、とあるきっかけからオルガンに関わる機会が増え、機械的な動作原理は、鍵盤からパイプまで基本的なところは把握しました。
とはいえ、これから機械の学科のお客さんを集めようというイベントで、これをやることには覚悟が要ります。え? なんでオルガン? という当然な反応を塗り替えて、関心を持って頂かなければなりません(いまご覧の読者の皆さんも、え? とお思いかもしれません)。今回、申し込み時点ではタイトルが出ておらず、来場時に配られた資料で気づくか、学科の部屋まで来て気づくか。実際、講義を始めた当初は微妙なリアクションを感じていたのですが、途中以降では皆さん熱心に聞いて下さっていたので、ほっとしました。
オルガンは発音する部分はパイプで、1本のパイプが1音色1音です。たとえば、管楽器の多くは操作で、弦楽器の多くは弦を押さえることで音の高さが変わります。一方、ピアノや木琴鉄琴は固有の音の高さのものを多数並べています。オルガンは後者の形式ですが、さらに1台で数種~2、30種の音色を持つ楽器で、多いとパイプ本数は数千になります。そのため、楽器としての特徴には、いかに音色をつくるかというパイプの工夫と、いかにそのパイプ群を演奏台の、主に一人の演奏者の操作で発音させるかという機械的工夫があり、モノや原理としてはかなり機械工学、さらにはメカトロです。
ということで、ちょっと意外性を狙って、機械の学科の模擬講義としてオルガンを投入してみた、という次第です。
楽器と固有振動数
われわれ機械系が固有振動数とか共振とか見かけると、まずは身構える、ぞっとするところから始まるのではないかと思います。積極的に利用する場合もありますが、電気分野ほどではなく、むしろ機械ではトラブルの宝庫です。想定外の大きな振動が起きたり、そのため異音騒音がでたり、繰り返しの荷重・変位で部材の破損につながったり。一方で、楽器の大半では固有振動が不可欠・前提の現象です。
楽器の音の要素は様々あります。第一に音の高さはメロディに不可欠ですが、音の高さは周波数です。楽器が安定して音を出せるのは、あるいは精密な調律ができるのは、その音の元となる振動が安定しているからで、固有振動の鋭さによります。同じ音を2台の楽器で出そうとして、両者の周波数が1[Hz]ずれていたら、1[Hz]のうわんうわんうわんといううなりが生じます。それを感じないということは、それだけ差がないわけです。実際にはその固有振動数はさまざまなものに影響を受けます。たとえば弦楽器だと弦の張力、オルガンのような管楽器は音速(空気の密度・温度等)の影響を受けるため、その調整(調律)があります。
楽器を特徴づける音色は、その音の波形の違いに現れますが、主には高調波成分の比率の違いです。機械振動でも振動の次数やモードは重要で、どの次数が共振するか、という文脈や解析がありますが、楽器の場合は整数倍の高調波は音色や、音を重ねるときに活用されています。分析してみると、10次以上までしっかりと続いていることもよく見かけました。
オルガンの場合は、発生させた振動をパイプで共鳴させて音色が定まりますが、多様な音色をつくるために多様なパイプ形状があります(振動の発生部にも工夫はあります)。おそらくは試行錯誤で特徴ある管を作った結果、特定の高調波の共鳴が強まるなどして固有の音色ができて、それが既存の楽器に近いから採用されたという歴史とみられます。管の形と音色を対応づける表現は文献等に見られますが、少し調べた範囲では論理的な裏付けはまだあまり進んでいないようで、研究調査の余地はまだまだありそうでした。
もう一つの特性としては振幅のエンベロープです。打楽器やピアノなどは、最初に叩くことで振動が始まり、それが減衰していく特性があります。あっという間に減衰してはテンポの遅い曲の演奏には使えませんし、なんらかの手段で減衰を強めたり、音を停止できないのも困ります。一方で共鳴を使う楽器は、振動の入力から共鳴(共振)で振幅が大きくなる過程で音が大きくなるので立ち上がりは少し遅く、入力がなくなると弦などに比べて短時間で減衰します。この特性は時間と言うよりは、波の数に支配されている感じで、本学のオルガンを聞いていても、周期の長い低い音のパイプは立ち上がりはゆっくりに感じられます。
というように、楽器は共振・次数・モード・減衰などの振動に関わる要素で成立します。あとは何でエネルギー・元となる波を供給するか、です。叩いたり、弾いたり、擦ったり、空気的振動だったり、弁構造の振動だったり。大学の機械分野では振動は大事な教育分野であって、前述のとおり、実践的機械屋にとってはなかなか縁の切れない相手ですが、楽器理解にも役立ちます。
楽器そのものの構造やメカニズム、製造など、機械工学が見た目で関わることは多いのですが、音についても機械のカバー範囲、ならば、機械の模擬講義でオルガンやってもいいかと思ったのですが、さて、その成果は2、3年後に「模擬講義聞きました、オルガンやりたいです」という学生さんが現れるかどうかを少しだけ期待して待ちたいと思います。
この記事は、会員専用記事です。
有料会員になると、会員限定の有料記事もお読みいただけます。





