
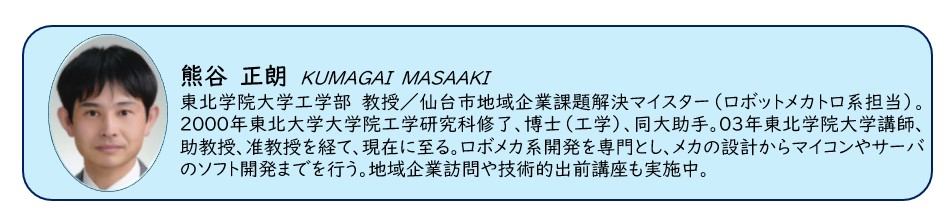
マッサージロボットの実用化
最近、SNSにマッサージロボットのサービスを受けたという米国の方の話が流れてきました。写真を見ると、ベッド的なものに、手先に押すための部品が付いたような6軸くらいの腕ロボットが左右に2本立ち、おそらくベッドの下にレールがあって、腕の台座が前後(人の上下)に動くように見えます。受ける人は寝転んで、ロボットで上などから押す、という動作が想定されます。それを見た私は「恐ろしい領域に到達したか」と反応し、それが軽くバズりました。
反応の様子からは「ロボットにされることが怖い」と解釈されたようなのですが、私の解釈はロボットによる対人サービスとして難易度が高くて怖い、手を出したくないと思うようなものなのに、それが米国で一般向けのサービスになったらしいということへの驚きでした。
しばらく前から介護支援ロボットやパワーアシストスーツの話題があり、近年は協業ロボットというジャンルがありますが、従来からの生産設備の様々なロボット、メカトロとは、ある点で大きく異なります。生産現場のロボメカ類は「人間と隔離する」ことで、対人の安全性を確保する手段があり、柵、箱、扉、センサ類による人間接近警報、などなどが使われています。少なくとも「扉を開けたら緊急停止」なら動作部に人間が巻き込まれる事故は防げ、装置の設計としては装置そのものだけについて事故無く動くことに専念できます(勝手に手を伸ばしてくる人間がいると想定すると、かなり面倒な不確定要素)。
ところが、対人の「力を出す」サービスでは、人に接したところで動作しなければならず、発想が大きく異なります。しかも、力が不足しても役に立たないため、相応の力、たとえば人間が出せる力やそれを越えるような力を出させるわけです。その制御にもしもがあった場合には、関連する人間にダメージを与えかねません。それゆえ、高度な安全性が、広範囲なシナリオでの想定で求められます。マッサージは「痛気持ちいい」という言葉もあるとおり、痛いと感じるような力も期待されるとともに、一歩間違えば怪我させかねないというすれすれのところゆえの難しさがあります。
マッサージをするには、位置の制御と力の制御のハイブリッドが必要といえます。たとえば、身体の表面のどの辺りを押すか、というポイントは(何らかの計測や情報に基づいて決定できたとして)精度を伴う位置決めが必要になります。一方で、押すときは押す力の加減が必要です。もし相手が固いものであれば、手先位置が接触する少し手前だと力は掛からず、逆に接触位置から押し込み過ぎた位置の場合はメカ的制御的剛性に応じた力が作用します。相手が筋肉のように柔らかければ、それも含めて大きな力は出にくくなりますが、骨に近いところでは大きな力が生じます。また、メカや制御の剛性を全体的に下げると動作の誤差や振動の問題が生じます。そのため、位置制御だけで力出力は難しく、押す方向は力制御、それ以外は位置制御(方向を定める動作含む)という組み合わせの制御が必要となります。
力のリミットと重力の便利さ
そもそも人によって、状態によってどういう施術が適しているかは多様であって、人間施術者によるマッサージ、カイロプラクティックや整体は訓練と知識と経験によって、また、被施術者とのコミュニケーションによって調整することを考えると自動化するのはかなり大変そうに思えますが、マッサージチェアを考えれば案外なんとかなる妥協点があるのかもしれません。この点は今回は置いておいて、どうやって事故の危険を低減するか考えてみましょう。
問題をシンプルにするために、「ある大きさ以上の力をかけたらNG」とします。もちろん、これは制御の工夫で「正常時には」可能です。力の制御ができるような工夫のされたメカであれば、直動の組み合わせでも、多関節の腕型でも、モータのトルク出力の計算などで実現できますし、手先に力センサをつけて、これをフィードバックして調整する手法もあります。しかし留意すべきは「動作異常時にも身体を危険にさらさないか」です。力センサが正しい計測値を出さなくなった場合、制御通信や制御ソフトの異常停止でモータへの指令が出っぱなしになるなど。
いくつか考えられますが、一つは被施術者の意思で逃げられるかどうか、もう一つは制御系が不適切な動作をしたとしても、メカの原理的にある程度以上の力は掛からなくする構造です。たとえば、以前から実用になっているマッサージチェアは、開放的な椅子の形なので人が簡単に脱出できること、マッサージの力は、寄りかかる身体の重みが上限(それを越えると身体全体が椅子から押し出される)という点で、これらを達成しています。一方、「肩をもむ(つまむ)」「頭(首)のツボを押す(頭を押さえながら)」ように挟み込むような動作の場合、今回見かけたロボットマッサージのような形態の場合は、人が逃げることはできず、かつ不具合時に最悪でメカが出せるだけの力がかかることになります。
もちろん、モータの出力を制限する(そもそもそこまで力の出ないモータを採用する)、という手法もありますが、1軸の押し込みはともかく、多軸ロボットの場合は腕を伸ばした姿勢でも必要な力が出せるように設計していると、姿勢によってはそれよりかなり大きな力を出せます。実際、カイロの施術などで、肘を伸ばして上から体重をかけることがありますが、これは肘や肩関節の筋肉を使って出せる力より楽に大きくできます(死点・特異姿勢)。それゆえ、実用的な出力と、個別の(ハード的)関節トルク上限はうまく両立できません。
解決策になり得る一つの方策は、「重さ」を力の上限にすることです。上記のとおり、マッサージチェアは、体重を元にした、もたれかかる力が上限になります。背もたれが立っていれば大きな力はかかりませんし、寝ていればそれだけ大きくなります。カイロなどでも上からは施術者の体重、横は床に対する摩擦力が上限になります(首の施術に被施術者の頭の重さを使うこともある)。それゆえ、寝転がって下からメカで押すような方式なら、いざというときに逃げられますし、最大は自分の重さ次第になります。ただし、背中や腰は良いとして、腕やふくらはぎなどは、下から押したら簡単に持ち上がってしまうので、上から別の重さで押さえる必要はありそうです。
しかし、この方法は床置きの腕ロボットでは難しそうです。床にネジ止めしたら前述の問題が、床に置いたところから横に腕を伸ばしたら倒れやすくなってしまいます。身体の上に乗っかって移動できるような、というと相当複雑になりそうです。
と、実用化は容易ではないだろうと考えていたので、冒頭の驚きにつながるわけです。子供のころのある時期、床にうつぶせの父親に「足の裏を踏んでくれ」と頼まれていました。当時、その意味が分からなかったのですが、今では私も同じような年齢になって、自分の子供に頼むことがあります。「ある時期」が比較的短く限定されることも分かりました。そもそも足裏という不安定なところに立てるだけでの身体能力が必要で、かつ、成長すると、この「重さによる力出力」が大きくなりすぎてしまうので。
この記事は、会員専用記事です。
有料会員になると、会員限定の有料記事もお読みいただけます。

.jpg)


