
目次
製造業DXnの今
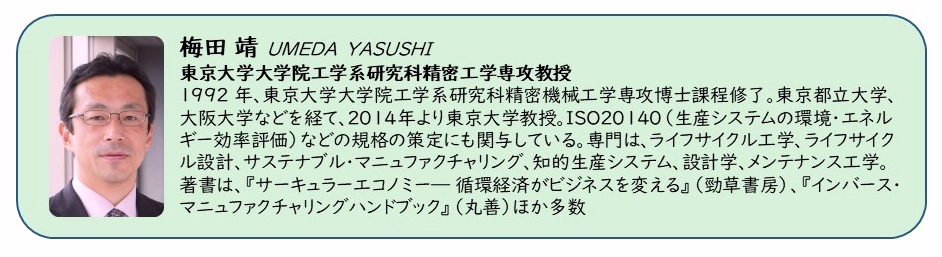
今年5月に開催された日本機械学会主催の講習会「競争力を高める製造業のDX化」に1日参加してみた。興味深い講演が並んでいたのと、自分の担当が最後だったので、なぜかフルで参加してしまった。
この講習会は日本機械学会の中の生産システム部門という割と弱小部門が企画したもので、東大の近藤伸亮先生と産総研の三坂孝志さんが企画と司会をしていた。今回は割とオムニバス的な話になりそうなので、最初に言いたいことを書いてしまおう。
筆者は割と突飛な「デジタル・トリプレット」(D3)という考え方を提唱しているが、もっとオーソドックスな製造業のDX化も着実に進化と深化していると感じた。例えば、産総研の高本さんが紹介してくれたドイツの最新動向は、向こうの厚みとパワーを感じた。これに対抗するのはなかなか容易なことではない。それでも、国内でも着実に進んでいるし、講師陣の間でやりたいことはかなり筆者と近く、日本のものづくりを強くするというのが1つの焦点であった。
とはいえ違うところもいろいろあって、例えば、産総研の古川さんのところはIoT化された試作工場を前から作っていて、データが沢山取れている。彼が中心になって作ったMZプラットフォームを使えば、かなり様々なデータを集めてきて、集約、可視化できる。その完成度は非常に高い。ただしご本人曰く「あまり面白くない」データとのことであったが、データは集まるが、トランスフォーメーションに持って行くところに距離があるといったことだと思う。
一方で、我々D3はデータの量が少なく、作業者にフォローアップのインタビューなどをしなければいけないので1つ1つのデータを取るのも大変である。ただ、コンテキストはリッチなので、使いではある。古川さんの話を聞いていると、取れるデータの量に雲泥の差があるし、古川さんのシステムが羨ましいと思った次第である。
もう一つ目からウロコだったのが、名古屋大学の菊地亮太先生の「データ同化」の話である。データ同化はご存知の方が多いと思うが、計算機のモデルがあって、シミュレーションをするのであるが、一方で、モデルに対応する実世界の実データが取得できる場合、その実データを逐次取り込むことによってモデルを補正して、シミュレーションの精度を上げて行く話である。菊池先生はこの分野の専門家で、気象予報モデルを例に話をされていた。
データ同化の話は理想的で、デジタル・ツインでデータ同化によってモデルをチューニングできれば素晴らしいと思っている。実際、気象予報モデルでは逐次大量の観測データを取り込んで、モデルをチューニングしてシミュレーションできているわけであるし。
菊池先生の話を聞いてみると、データ同化の方法というのは相当に作り込んでいるようであった。つまり、シミュレーション結果と実データの間にどういう差分があったら、モデル上のどのパラメータを調整して合わせるかといったノウハウが相当詰め込まれている印象であった。例えて言うならば、モデルとそのデータ同化の方法が、ノウハウが蓄積された一つの芸術作品のような印象を受けた。う〜ん、それだと筆者のやりたいこととちょっと違うかな、個々のモデル、例えば生産システムのモデルをそんなに作り込むパワーはないし。しかし、菊池先生は大規模な気象予報モデルだけではなくて、バイオガス発電プラントや超有名酒造プラントの制御も上手くやっている。一昔前に流行ったデータアナリティクスや、機械学習や今で言うとLLMの使いこなしのように、職人芸的なデータ同化ノウハウ技術体系のようなものの存在を感じた。
その他の講演と概要は以下の通り。
1)「製造業におけるデータ活用にむけた国内外の取り組み」(産総研 髙本仁志氏):日米独を比較しなが
ら、製造業におけるデータ活用の最新動向をまとめてくれていた。ちょっと気になったのが、Digital
Product Passportという(この連載でも何度も出てくる)サーキュラー・エコノミーのためのツールが
当然のように出てきていること。ドイツでは、製造業のDXとサーキュラー・エコノミーの垣根がない
のだなとつくづく思った。
2)「エンドユーザ開発に基づく製造現場のDX化」(産総研 古川慈之氏):前述
3)「デンソーのモノづくりとDX推進」(㈱デンソー松永泰明氏):やっぱりデンソーは、この分野で我が
国のメーカーの最先端を行っていると思った。お金があるし、生産にかける人的、技術的、経済的リ
ソースが飛び抜けている。車の電動化に代表される事業環境変化、不確かさに対応した生産システム
を考えているところがすごい。この話はまた近日中に書きます。この中に出てきた、
・デジタイゼーション:データの転記などの工数削減による余力創出
・デジタライゼーション:データをつなぐことによるロス最小化
・デジタル・トランスフォーメーション:サイバー空間をフルに活用して、ひとりひとりの未来のアイ
ディアを形にして、業務スピード・質向上
というのは重要で、非常に分かりやすい。
4)「デジタルツインとデータ同化による製造プロセス最適化に向けて」(名古屋大学/DoerResearch株式会
社 菊地亮太氏):前述
5)「LLMと科学的方法を活用した製造DX 〜プロンプトエンジニアリング、CAE、予測保守、サロゲー
トモデルの実践〜」(大阪成蹊大学 小山田耕二氏): LLMの解説とプロンプトエンジニアリングによ
る製造業のDXの試み。流体シミュレーションのようなことがLLMでできてしまう、結構驚き。LLMの
可能性を引き出し、役に立たせようとしている先生方は結構いる。
6)「人を中心にした製造業のDX化 〜 Digital Tripletのアプローチ」(梅田):いつもの話
いろいろ考えさせられる、意義のある講習会であった。
この記事は、会員専用記事です。
有料会員になると、会員限定の有料記事もお読みいただけます。




