
目次
CEコマース
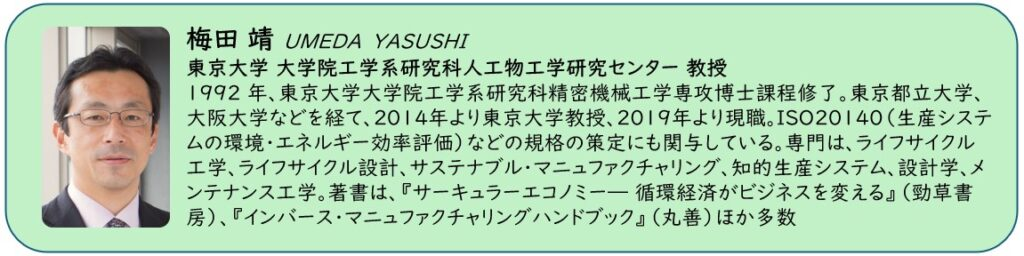
CE (サーキュラー・エコノミー)コマースのガイドライン「CEコマースビジネス推進のためのガイド」がCPsのホームページから公表された。CPsというのは、経産省が主導する、CE実現に向けた産官学パートナーシップ「サーキュラーパートナーズ」の略称である。Webで検索すればすぐ出てくる。
「CEコマース」は、経産省と私の造語であり、このガイドラインでは、シェアリング、レンタル、リースなどの「物品の稼働率を高める」、二次流通仲介、中古品売買、リースなどの「物品の利用期間を延ばす」、そして、リマニュファクチュアリング、リファービッシュ、リメイク、リノベーションなどの「物品の寿命を延ばす」の3つのパターンで整理している。ちなみに、二次流通仲介というと、例えばメルカリのように、自社が中古品を売買するのではなく、その仲介をするだけという意味で、中古スマホ販売やブックオフのような中古品売買とは区別されている。
この3類型は、残念ながら、純粋な日本オリジナルという訳ではなく、EUタクソノミーの中で、割と詳細な分類が行なわれている。ちなみに、EUタクソノミーというのは、持続可能な投資を促進するためのEUの法規制で、金融機関が投資対象としてよい「持続可能な経済活動」が何かを定義するリストのことである。このリストから漏れると、その企業活動は「持続可能な投資」と認定して貰えない恐ろしいものであるが、そうは言っても、基本は金融機関による投資を縛るという間接的なものである。一方で、今回のCEコマースのガイドラインは、今年6月までやっていた国会で成立した、改正資源有効利用促進法に連動したもので、こういった業界は役所と関係が薄かったものを、ちゃんと経産省が業界と連携して、業界の育成、消費者保護を進めながら、健全に市場形成して行きましょうということになっている。
このガイドラインには、上記の3類型に関連したビジネスモデルの整理、取組事例などが並んでいる。メンテナンス関係も多く含まれていて、なぜか、「リペア・メンテナンス・レストア・クリーニング」という分類になっていて、リペアはメンテナンスの一部ではないのかと思うものの、各業界の習慣によるところが多いようである。ここに書かれているように、なんと、街のクリーニング屋さんもCEコマースということになっている。
25年1月号の本連載に少し書いたが、最初、経産省はリコマースで行きたいと言っていた。リコマースというと、中古品の買い取り、流通、3類型でいうと「物品の利用期間を延ばす」のみに該当するだろう。それじゃ狭すぎるからということで議論して、CEコマースという言葉になって、「物品の稼働率を高める」、「物品の寿命を延ばす」が入って本当に良かったと思っている。
今回のガイドラインはほぼほぼB2Bは入っていなくてB2Cのみであるが、それにしたってかなり広範囲のビジネスをカバーしている。クリーニング屋さんも含めて。よく、CE市場規模を2030年までに50兆円から80兆円に(環境省調べ)といったキャッチフレーズが出てくるが、これはほぼほぼ旧来の3R関連産業しか入っていない。筆者の野望は全製造業、全サービス業がここにカウントされることであり、今回のCEコマースという括りは、この野望に一歩近づいたことになる。ただし、単に定義を変えて水増ししただけでは何の意味もないのだが。
ちなみに、CEビジネスの分野で名高い、敬愛するS先生は、およそCEコマースに相当するところを「中脈」、つまり、動脈、静脈の間、という名前で呼んでいて、その重要性を5年前から指摘していたとのことで、なるほどと感心する次第である。多分、「中脈コマース」という名前は採用されなかったとは思うが。
関係者の話を聞いていて思うのは、今回は3類型で上手く整理したが、なかなか分類にのらないビジネスのパターンがいろいろあるし、業界によって言葉の意味が全然違ったりしている。さらに、例えば、リースと言ったところで、その中には様々なビジネスモデルがあって、様々な類型に顔を出す。その辺を言葉として整理するのが非常に難しいと感じた。さらに、例えば、メーカーが複写機を再生して、新品同様にして品質保証して出すリマニュファクチャリングと、ユーザーから買ったiPhoneをちょっと清掃して店頭に並べる中古品販売を同じ「CEコマース」としてしまうのか、大変さなり、技術や必要な資本が全然ちがう、といった考えもある。この点は割と簡単で、循環を成立させるやり方は、製品、ユーザー層、求められる価値などによって多様であって、様々な業態が組み合わさって補いあい、全体としてCE社会が形成されるのだと思う。いずれにせよ、こういったごちゃごちゃした概念を事務局はよくここまで整理したと褒めてあげたい。
CEコマースという言葉が一過性で、役所が旗振ってコケた、ということにならないで、この分野が成長して、生活者が便利に感じて、Well-beingの向上に役立ち、なおかつ、日本全体のCO2排出量、資源消費量、廃棄物量削減に結びつくことを願っている。そもそも、この分野は、デジタルを活用したスタートアップがいろいろ入って来て活性化したという側面が強いので、旧来型の役所による育成?介入?保護?規制?といったものが馴染むのか、逆効果にならないと良いが。いろいろハードルは高い。
この記事は、会員専用記事です。
有料会員になると、会員限定の有料記事もお読みいただけます。


.jpg)

