
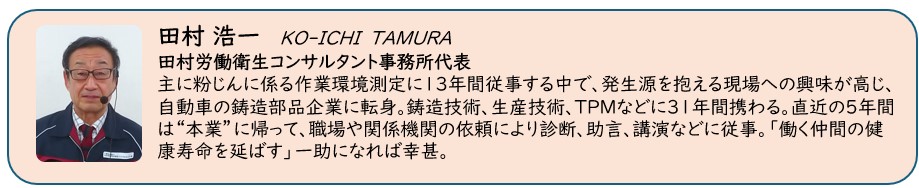
対策と改善
30年以上前の鋳造工場の現場風景である。「朝市ミーティング」と称し、前日発生した不良品を前に、「対策」に明け暮れていた日々があった。素材不良率は5%を下回ることはなく、型式によっては10%~30%も当り前。つくってもつくっても不良。「現場が泣いている!」と叩き上げの職長から生産技術者たちに対する、半ば恫喝のごとき追及は止まず、原因も定かではない中、何か行動をと「対策」が講じられる。後工程の加工からは、「素材屋は原因も分からないのに対策か」と嘲笑。本格的にTPMを導入する以前のことではあったが。
後に知るところである。「ものづくり屋は、極限追求を掲げ、後戻りしない継続的改善を『正』とすべし」しかし、成果が要求スピードに追い付くまでには、方法論とともに訓練と実践の積重ねが必要だ。国語辞典的には「対策とは、相手や問題に対応すること」。「改善とは、改めて良くすること」が共通、さらに、対策には“個別でそのとき”、改善には“長期的”といったニュアンスが加わる。鋳造の不良対策として「合格基準を緩和してもらう」などという「まさに相手への対策」まで飛び出したことがあり、笑えない笑い話であった。
この記事は、会員専用記事です。
有料会員になると、会員限定の有料記事もお読みいただけます。
新着記事

せつびさんとカンリさんの「モノづくり品質の基本のキ」#10 良い仕事をするための基本~その8 「事実に基づく管理 管理のサイクル」
2026.01.15

ものづくり屋視点による労働衛生の実践 No.10 メンタルヘルス問題の認識と向き合う活動―その1
2026.01.15

指標でモノづくりを評価しよう! #9 生産リードタイム
2025.12.24 無料会員

DXの活用がカギ! 生まれの良い設備づくり ①
2025.12.24

せつびさんとカンリさんの「モノづくり品質の基本のキ」#9 良い仕事をするための基本~その7 QC7つ道具⑤
2025.12.17

ものづくり屋視点による労働衛生の実践 No.9 旧い問題だが、終わってはいない石綿含有材の取扱い
2025.12.17

