
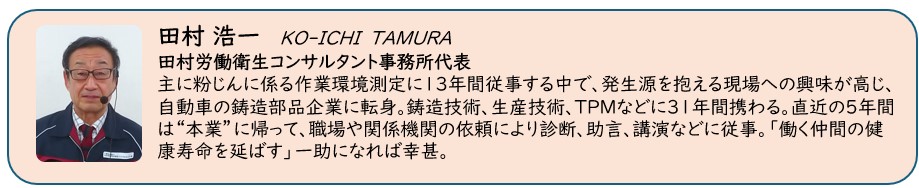
全国労働衛生週間が始まる
間もなく10月1日~10月7日の全国労働衛生週間を迎える。9月はその準備期間とされ、すでに労働衛生旗(第1回で紹介した“逆ミドリ十字”)を掲げている事業所もあろう。労働衛生を活動の場としている筆者としても、今月はぜひ表題についてお話し、併せて本連載の全体像の中間確認としたい。
7月に実施される安全週間の方がなじみ深いかも知れない。この開始が1928年であることに対して、労働衛生週間は1950年を第1回とする。かなりの時差があり、しかも戦後のスタートなので、当初より進歩的・合理的だったのかというと必ずしもそうではなさそうだ。
活動には、目的・目標や課題設定、計画などが付きものであるとして、労働安全衛生法(以下、安衛法と略記)第6条には「労働災害防止計画(以下、災防計画に省略)」と言う、国が定めるべき計画が謳われている。この計画は、1958年の第1次より、5ヵ年計画で更新され続け、現在第14次計画が進行中である。労働衛生週間で事業者に推奨されている活動の中身と、国の責任で策定されてきた5か年計画の課題とを、この機会に時間軸で対比させながら振り返り、現在の到達点を確認するとともに、近未来の模索をしてみたい。
この記事は、会員専用記事です。
有料会員になると、会員限定の有料記事もお読みいただけます。





