
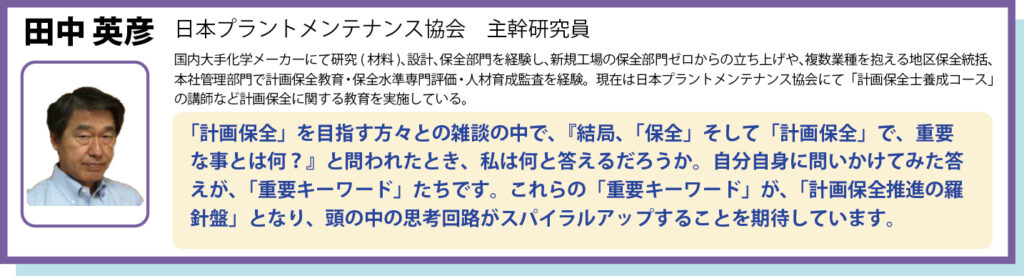
羅針盤その10 「人は宝」
「計画保全」では、“ジンザイ”を記す際、“人材”ではなく、“人財”との漢字を適用する。
英訳するとどちらもHuman resourcesになるかもしれないが、漢字は明確だ。読んで字のごとく、“人は財産だ”と認識できる。“保全に関わる人は宝ですよ”と認識してほしい。
宝を育てる「人財育成」は、事業貢献に直結する必然経費・必要時間だと考えることで、自ずと、人財に関わるプログラムの構築が、組織の一職務と認識できるはずである。
保全に関わる人には、あるレベル以上の技術力が一律に求められる。そのための種々の仕掛けを考えて欲しい。
「計画保全」では、人財育成のための、基本方針の策定・職務プロファイルの設定・教育到達レベルの設定・教育ガイドラインの作成・個人別育成表の適用などが推奨されている。その種々の例は、非常に参考になる。
また、「保全水準評価」の狙いの一つに、人財育成が掲げられている。水準評価を定期的に実施する中で、保全メンバーの意識づけが強化され、育成の効果も生まれる。
どのような保全を目指すかを最初に考える必要があるが、この目指す保全とリンクして、どのような人財を育てるかを重要視したい。
保全に関わる人は、“技術屋”であることを自認し、日々技術の研鑽を積む必要がある。
保全職務の遂行には、非常に多種の技術領域が関係している。設備を最も深く広く熟知しているのは保全メンバーであるため、工場や事業部から非常に頼りになる存在(=人財)として認められている。また、そうあらねばならない。
さらに、保全の仕事は、改良・改善の知恵が必要とされる機会が多い。
故障が発生した場合は、あらゆる保全技術を総動員させて、真の原因を追究する必要がある。長く使用するためには寿命を予測する必要がある。時代が進み、技術が進歩しても、従来からある技術的要素は、引き続き重要な要素となる。設備管理の広がっていく技術領域に、“溺れる”ことなく適切に使いこなしていく必要がある。
各企業で整備されている保全人材育成プログラムを見ると、必要とされる機能や、必要な技術・技能が多岐にわたっていることがわかる。社内での職階が上がるに従い、要求される技術領域は広くなる。さらに管理職になると、技術領域に留まらず、事業に大きく関わる長期的視点や大きな予算に関わる判断が求められるのだ。
誰から見ても、広く高い技術力を持っているなと認められるように、日々研鑽を積む必要のある職務が保全である。宝と位置付けられた「保全技術者」は、これを自覚し、技術力をさらに高めようとの意識を持って、日々の業務に臨んで欲しいものだ。
「人は宝」であることを常に意識しよう。
●重要参考テキスト
・『MOSMS実践ガイド』(p305:人財育成、日本プラントメンテナンス協会)
・「計画保全士養成コーステキスト」(p128:人財育成、日本プラントメンテナンス協会)
おわりに
保全の仕事は、日々未知の出来事との出会いである。その瞬間は大変だが、恐らくドキドキ感がたまらなく心地よいはずだ。
対応には、多種・多方面の技術力の結集が要求される。日々興味を醸し出し、日々の研鑽が必要とされる。“技術屋”として、ここまでの総合力が必要とされる職務は、他にはそうないであろう。
多様な仕事がある中でも、保全の仕事は、知的動物として生まれてきた我々人間にとって、最も相応しい職務の一つに数えられるのではないだろうか。
しかも、日々の仕事の成果や、年間の仕事の成果は、直接に事業貢献に寄与できる。“モノづくり”という日々創出&進歩を続ける産業界に就いた我々にとって、仕事冥利に尽きるというものだ。
・履歴という大切な宝を、一つひとつ、一枚一枚積み重ね、太い柱を構築したい。
・太い柱の歴史を重要視しつつ、且つ新しい情報も貪欲に取り入れ、次のステップを自ら考えていきたい。
・なぜなぜと常に問いかけ、真のメカニズムに辿り着きたい。
・一時一時を大切に、隙を与えず、継続性を醸し出したい。
・自分の仕事を愛し、任された設備を愛したい。
・財産と位置付けられた自らを自覚し、個人力およびチーム力を最大限に発揮したい。
この記事は、会員専用記事です。
有料会員になると、会員限定の有料記事もお読みいただけます。

