
目次
精密工学会技術賞
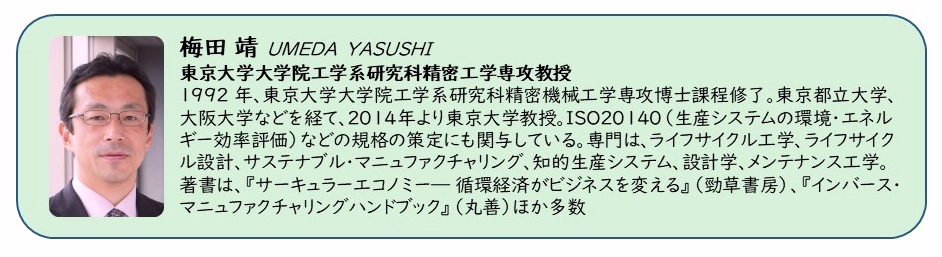
先日、精密工学会技術賞が発表され、その一つにデンソーの「不確実な事業環境を勝ち抜くトリプルS生産システム」が選ばれた(https://www.denso.com/jp/ja/news/newsroom/2025/20250919-01/)。これは、デンソーの大安工場にある、可動式モジュールによる、かなり高度なスマート生産システムで、一度見学したことがあるのだが、大変面白かった。
トリプルSというのは、Sustainable(持続可能)、Smart(デジタル化)、Sensible(高感度)の意味で、若干こじつけの感があるが、システム自体は画期的だと感じた。基本、フローショップ方式の生産システムで、真ん中に搬送ラインがあって、そこに加工、組立などの機能を果たす設備モジュールを適宜接続して、多様な製品を製造できるようになっている。設備モジュールは、サイズと接続インタフェースが標準化されていて、AGVで簡単に移動できるようになっていて、自動でラインに接続できる。接続部分が工夫されていて、剛性も確保できるし、電源、通信、エア供給も自動で接続できるようになっていたし、遠中近3段階の位置補正技術を開発したことにより、加工、組立に必要な精度を自動的に確保できるようになっている。
この生産システム、幾つか感心した点があった。まず、デンソーという自動車部品メーカーの立ち位置との関係である。自動車部品は、今後、電動化が進むと言われているが、トランプ現象を見るまでもなく、その進みは行きつ戻りつで、予想し難い。とすると、自動車部品メーカーとしてはガソリン車からEVまで多様な自動車部品を用意しなければならないし、各部品の需要量も予測し難い。そこで柔軟に組み換えられて多品種少量生産への柔軟性と、いざ沢山作るとなったら従来の専用ラインの効率性とを両立する生産システムを作った、という説明であった。多品種少量生産ならばセル生産方式もあるだろうが、フローショップ方式にこだわるあたりがデンソーらしさなのだろう。いずれにせよ、将来に対する問題意識が生産システムの形として現れている一貫性が素晴らしいと思った。参考資料によると、ライン新設時にリードタイムが30%短縮、さらに、変化対応時には90%短縮すると言うことである。
もう一つ面白いのは、生産システムとしてはモジュラーなのに、それが製品設計、工程設計、生産システムというエンジニアリングチェーンを通じてインテグラルになっているところである。つまり、この生産システムをモジュラーにするために、要素工程を8種類に絞り込み、この生産システムで作る製品に関しては、この8種類の工程、このサイズの生産設備で作れるように製品設計にも、工程設計にも制約をかけている。このように部門の壁を越えて上手いこと標準化のすり合わせができるところが日本式ものづくりだと感じた。もちろん、設備モジュールは、ある生産ラインでの生産が終わっても別のラインに簡単に転用できる。この辺がSustainableに通じる。
と、ちょっと筆者自身でも気持ち悪い位、べた褒めしている理由は、筆者自身色々なところで、1990年代前半はIMS (Intelligent Manufacturing System)プロジェクトなどで、日本から新しい生産システムの方式が次から次へと提案されていたがそういうのが絶えて無くなって、今は、インダストリー4.0にやられっぱなしじゃないかと言ってきたからである。しかし、この工場の人達と話すと、多品種少量生産を狙うと例えばインダストリー4.0を代表するKukaのAGVを活用したマトリックス・生産システム(https://www.facebook.com/watch/?v=10155419198011956)などになるが、あれば頭で考えた方式だろうと。こちらはちゃんとユーザ(工場操業者)の視点を入れて、きめ細かい配慮を加味して、ちゃんと使える、専用ラインの効率性と、多品種少量生産への柔軟性を両立できるように作ってある、と言う。本格展開はまだまだこれからのようだが、この辺のきめ細かさでまだまだ強みがでてくる、そういう我が国発の新しい生産システムの方式の提案だと感じたので、べた褒めしているのである。
そうそう、この大安工場はデジタル・トリプレットも標榜していて、工場全体がもちろんフルIoT化、見える化されている上に、QC7つ道具のデジタル版であるDN(Digital Native Quality Control)-7つ道具が用意されていて、(こういう言い方は良くないのだが)若い女性達が現場でサンキーダイヤグラムなどを作りながら、デジタルをフル活用したカイゼン活動をやっていた。この辺も、日本型ものづくりの未来が垣間見えた気がした。
参考文献
松永泰明:デンソーのものづくりとDX推進,日本機械学会No.25-58,講習会「競争力を高める製造業のDX化」,2025.
この記事は、会員専用記事です。
有料会員になると、会員限定の有料記事もお読みいただけます。





