
長寿命化は経済にプラスになるか
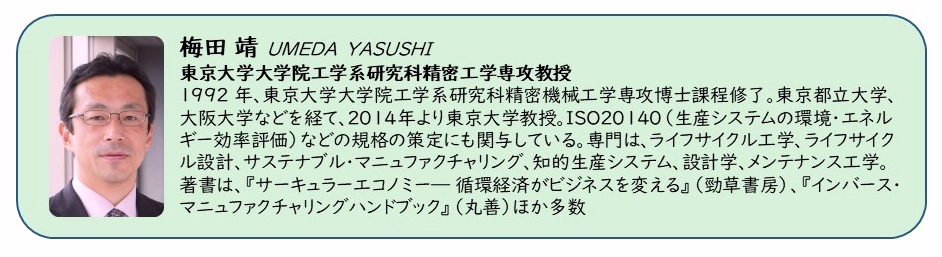
先日、サーキュラー・エコノミー広域マルチバリュー循環研究会(CEMVCで検索すればすぐに見つかります)という研究会で「長寿命化は経済にプラスになるか」というお題でしゃべれという依頼を受けた。この研究会はいつもかなり濃い議論をするので面白かった。
一つ再認識したのは、製品のカテゴリーやB2BかB2Cかなどによって状況が異なるということである。例えば、橋、高速道路などの社会インフラは、そうそう壊して作り直すという訳にも行かないし、今の日本にはそんな国力も無いであろうから、長寿命化が基本戦略になるだろう。
この研究会のお題が、環境に良いか、ではなく、経済にプラスになるか、としているところにヒネリが加えてあって(私はこの研究会の運営側ではありません、念のため)、社会インフラの長寿命化は、インフラ更新需要を喚起しないという意味では経済にプラスじゃないかも知れないが、どうせ更新する国力も無いのだから、メンテナンスしないで高速道路や橋が使えなくなるよりは経済を活性化することに貢献するだろうから、プラスと考えても良いのかもしれない。
モノの長寿命化と経済の関係は単純じゃないので、難しい。建築の世界では、スケルトン・インフィルという技術が昔からできていて、これは、寿命の長い躯体と寿命の短い設備を分離して、寿命の短い部分を交換可能にすることによって、スケルトンの部分を半永久的に使えるようにする技術である。
建設会社の人に話を聞くと、技術としては確立しているが、施主が望まないので結局、建て替えになるということであった。逆に、半導体製造装置、EV用バッテリーなどの分野では、性能向上こそが価値であり、停滞は負けを意味するので、長寿命化はあり得ないという声が多かった。この辺は、後述するように上手く設計すればもう少し何とかなると思っているのだが。
さて、これら以外の工業製品、例えば、自動車、家電、パソコン、工作機械あたりはどうであろうか。議論が2段階あると思っている。
まずは、顧客(B2Cなら消費者、B2Bなら企業)が長寿命な製品を選ぶかどうかという選好の問題と、長寿命な製品が選ばれたとして、それが経済のプラスになるかという経済システムの問題である。選好の問題に関して言えば、長寿命製品は長く同じものを使えて、製品を入れ替える負担もないし、新しい製品の使い方に習熟する必要もないというメリットがある一方、デメリットとしては、劣化により壊れやすくなる、新製品が欲しい、新製品に比べて技術が古い、機能が劣る、省エネ性が劣る、新製品に比べて汚い、長期使用後に修理しようとしても部品が手に入らない、メーカーがなくなっていて修理できない、修理コストが高い、最悪、製品価格と逆転する、などが挙げられるだろう(他にもあるか?)。
私自身の信念としては、これらの問題は設計と製品使用時のサービス提供によって、ほとんど回避できると信じている。例えば、新製品に比べて機能が劣る、技術が劣るという課題に対しては、先に挙げたスケルトン・インフィルのように設計し、製品を適切に切り分けて、モジュール単位で入れ替えられるようにし、使用時にモジュールを適宜入れ替えるようなサービスを提供すれば良い。工夫次第で解決できると思っている。
一方、経済システムの問題は難しい。ユーザ視点で「長期使用の方が割安」ということであれば、それは経済にマイナスということであり、ここが多くの企業が嫌がるところである。つまり、大量生産・大量販売を前提とする「量」の経済システムの中では、長寿命化は経済規模を縮小させ、デメリットでしかない。量から離れ、得られる価値にお金が払われる経済システムに転換できれば、長寿命化はメリットになる。このような経済システムの中では、現代の製造業の中の過剰生産部分が除去され、「適量」生産構造を作らなければいけない。
さらに言えば、長寿命化=1ユーザによる製品の長期使用とは限らない。中古スマホやメルカリ、若者の古着ブームに見られるように、中古市場は確実に広がっている。(私も片棒を担いでいるが)経産省はこれをCE(サーキュラー・エコノミー)コマースとして流行らせようとしている(本連載でも触れたような気がするが)。
CEコマースの視点から見れば、製品が上記の様々な課題を解決して長寿命化すれば、メンテナンス市場や中古市場が活性化するし、例えば、カーシェアリングビジネスにとっては自動車が長寿命化になればなるほどコストダウンになる。製品がダメでも部品単位で長寿命化できればリマニュファクチャリングビジネスが活性化するし、メンテナンス時の交換部品として活用できるのでコストダウンになる。
その意味でモノを作るだけの製造業の規模は日本全体では小さくなるかもしれないが、こういったCEコマース産業が拡大すれば、ものづくりとCEコマースに代表されるサービスビジネスの合計で経済成長に繋がるはずである。
言ってみれば、現状は、生産設備がフル稼働することによるコストダウンを目的に量の経済が回っている。それは早晩成立しなくなり、生産は最低限に留め(それでも生産技術向上によるコストダウンの体制は維持したい)、作った製品をその寿命が尽きるまで何度も使うという意味で製品をフル稼働させる社会に変わらなければならない。この変化が長寿命化が経済にプラスになる条件であり、逆に、長寿命化が顧客に受け入れられれば、こちら側の社会への移行が進むと思った。
この記事は、会員専用記事です。
有料会員になると、会員限定の有料記事もお読みいただけます。




