
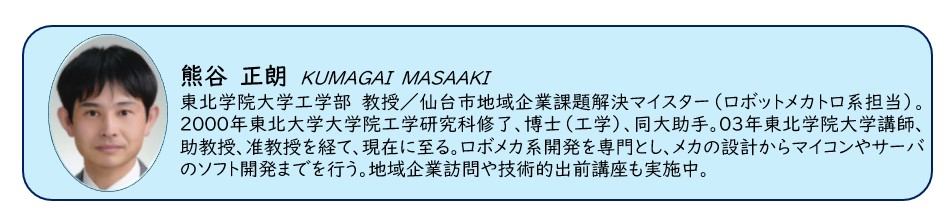
100年前の機械装置
最近、学内にひっそりと残されていた、約100年前の機械装置の解析をしていました。いずれ研究プロジェクトの成果として発表することになるので、まだ詳細は控えておきますが、周辺の情報からすると1930年ころに開発・製造されたことは間違いなさそうです。気圧と電気信号で動いていた装置で、配線は至る所で朽ちて、空気系の素材も劣化して破れたり、パリパリになったりしていましたが、機能の把握はかなり進みました。
この装置はある種のプログラムデータに基づくシーケンス動作をするような装置で、そのデータの読み取りや駆動に空気圧系の手法を、データに基づいた出力やモード(ステート)の変更などに電気を用いています。時代が時代なので、エレクトロニクスではなく、エレクトリック、「メカトリ」でしょうか。それゆえ、空気圧系の回路もあれば、リレーによる自己保持らしき回路も見られますし、一番大きい物では70接点くらいの巨大リレー(?)もありました。
この装置を見てすぐに、負圧で動作する機械だと気づきました。チューブがいかにもな肉厚でした。今日の機械装置、とくに工場の生産設備の分野ではエアのアクチュエータは多量・多様に使われていますが、基本的には正圧です。おおむね数気圧・0.数[MPa]でしょうか。その発想からすると、「え?負圧?なんで真空ポンプみたいなのが付いているの?」という疑問からのスタートです。この装置のデータの読み取りの方式上は、正圧より負圧のほうが合理的と確認できるのですが、負圧でも機械が動くのかという関心がわきます。
たとえば、直線的な運動をする部分では、伸縮するベローズ構造をバネで引き延ばしておいて、負圧源からの配管をつないで中を減圧すると、大気圧に潰される形で縮み、中を大気圧に戻すとバネで伸びます。この原理の圧力レギュレータもありました。あるいは、ベローズ2個を逆向きにつなぎ、減圧した方が潰れてもう一方を引き延ばす、ようなペアもあります。正圧によるシリンダが、両側から押し合うことで双方向の移動をすることに対して、負圧で引き合うことで動くような感じです。さらに、この構造とクランクを組み合わせた負圧エアモータまでありました。詳しい方によれば、当時のそれらの機械はせいぜい、今の一般的掃除機の吸引よりも弱い負圧で動いていたとのことですので、似たものを作ると「掃除機で吸うと回るなにか」ができるわけです。
他の部分も確認したところ、正圧でなければ動かないようなところもあって、正圧をどうやって用意しているのか探しました。正圧のエア主体のときに、少量の負圧を作る部品に真空発生器・エジェクタがありますが、それに類する物か、あるいは機械的ななにかかがあるのだろうかと。結果的には、外部につながる出力配線に隠れて、正圧の供給を受けていたとおぼしき配管が見つかりました。だったら全体的に正圧で、と思うのですが、この業界は正圧もさほど圧が高いわけではないので、装置の主たる部分は負圧で、ということだったのかもしれません。
正圧か負圧か
というような歴史があったとすれば、現代にももう少し負圧で動く機械があっても良さそうな気がします。少し探してみると、自動車用アクチュエータで、「エンジンが空気を吸い込むときの負圧」を利用するものがありました。排気側は正圧が使えそう、とも思いましたが、排気は高温ですし、吸気側は追加装置無しでタダで負圧が得られそうです。
生産設備系ではエアのアクチュエータ(主にシリンダ)が広く用いられていますが、一部で吸着が必要なところで負圧を使うほかは専ら正圧です。いくつか理由は考えられますが、おそらく一番の理由は動力として使うためです。圧力を利用するとき、基本的には「差」を使います。何かに対して作用する相反する「圧の差」で力が生じ、それに流体の移動に伴う移動速度が掛け合わされると動力になります。この力は「圧×面積」で生じるため、シリンダのようなシンプルな構造であれば、そのピストン断面に対して両側の圧力×面積の差が生じる力になります。断面積は概ね両側で等しく、面積×圧力差となります。シリンダの一方にはコンプレッサからのたとえば0.6MPa(6気圧, 真空基準の絶対圧で)がかかり、もう一方が大気に解放されていれば0.1MPa(1気圧, 同)で、その差0.5MPa分が力になります。より高い圧力を使えば、より大きな力が得られます。
一方で、もし負圧側を使ったとしたら。負圧とは大気圧を基準すればマイナスの状態ですが、真空を基準とする絶対圧ではプラスです。絶対圧でのマイナスはありません。そのため、一方が負圧、もう一方が大気圧という使いかたでは最大でも、差が0.1MPaにしかなりません(その上、0MPa=真空に近くなってくると圧力を下げることがかなり大変になるので、現実的には0.05MPa程度とか)。そのため、「力を得るための圧力差」と考えたときに、負圧を使うことはかなり不利です。負圧で物を吸着することも、吸着する面だけ圧力を下げて残りは大気圧で押してもらっているという差を使うので、吸着で力を大きくするには面積を稼ぐくらいしか手はありません。
このことから、動力出力を考えたときは、大気圧を基準として制約の厳しい負側ではなく、正側を使うことに大きなアドバンテージがあります。おそらく、他にも「吸い込む」の場合には吸い込むところでゴミなどが入らないようにという気を使う必要もあると思われますが、吹き出すならその心配はいりません。
これに対して、同じ「圧」という言葉を使う電圧については、必要に応じて正も負も両方等しく使えます。マイナス側には(不慣れということを除けば)目立ったデメリットはありません。たとえば、昔あったECLと呼ばれる形式のデジタル回路は -5.2Vの電源で動作するものでした。単純には、[-5.2V,0V]で動かすのも、[0V,+5.2V]で動かすのも電気的には同じなのに、なぜ-5.2なのかが気になっていましたが、「電気的に安定性が必要な配線」が高い方で、そこを変動しにくい0に固定した、ということのようです。
前半で述べた装置は、原理的にはこう動く、というところは解析して概ね理解できましたが、実は「なぜうまく動くか」で不明点が多く残っています。というのも、リレーはもちろん、気圧によって動く部分はその動作に遅延が生じ、かつオンになるときとオフになるときで反応速度に差があります。どうやら、その遅延の微妙な差に依存している、一見デジタルの振りをした、かなりアナログ特性のものではないか、と見えてきたからです。これについては、今後解析を進めていこうと思っています。100年前に、よくこんな装置を作って販売していた(=思いつきの試作品ではない)ものだと思います。この装置の機能を少しずつ読み解いていくことは、今の「楽しい仕事」の一つになっています。
この記事は、会員専用記事です。
有料会員になると、会員限定の有料記事もお読みいただけます。






