
「点検員の熟練知」
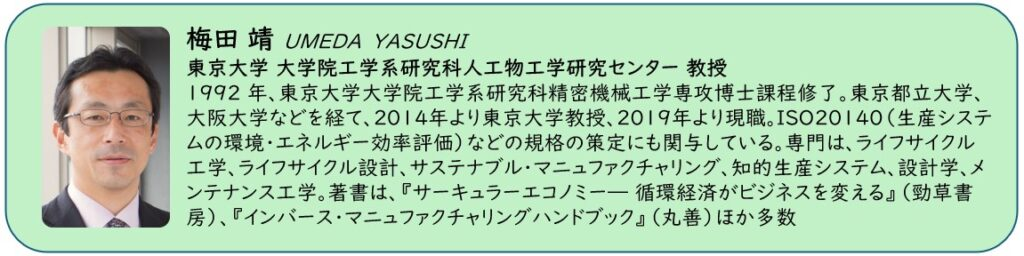
たまには、「プラントエンジニア」に近い内容の話をしよう。
以前少し触れたのだが、企業との共同研究で、プラントの点検作業における、熟練者と未熟練者の行動の違いを分析している。
なぜ、熟練者は、他の点検員が気付かないような不良の兆候を見付けだすのか? そこから、熟練知を探り、作業支援や自動化に繋げようというねらいである。
大きな課題はご多分に漏れず、労働力不足と熟練者の引退とそれに伴う熟練知の喪失である。学生が、点検員について回り、ビデオ撮影や作業の分析をして点検員にインタビューを行った。かなり手間のかかる研究である。
たとえば、あるプラントの同じ場所で、熟練者3名、未熟練者3名それぞれの実際の点検作業の記録をとって比較した。もっとも興味深かったのは、熟練者の間でも、点検ルートも点検箇所も様々であった点である。もちろん、法規は満たされているし、このプラントには基本的な点検マニュアルもあり、それは基本的には満たされているのだが、その上で、多様であった。
むしろこの多様性によって、プラント全体の点検がカバーされているようにも見えたが、管理者側も、熟練点検員同士も、これらの点検ルートや点検箇所の相違を意識していないようであったし、情報交換も調整もしていなかった。この辺は謎であった。
熟練者と未熟練者の違いに関して、とりあえずのわれわれの整理は、熟練者は、どの点検ルートを通るかとか、各機器を点検するとかしないとかということについて、それぞれ根拠があって、説明できる。たとえば、ある機器を点検する際に、1人の熟練者は触って振動を確認していたが、残り2人の熟練者は触っていなかった。
それぞれがその行動の根拠について、説得力のある説明をしてくれた。
その根拠となるものは、各自が持っている行動原理(点検できるものは極力点検する、できるだけ効率良く情報収集するなど)と自分なりのリスク評価(この種類の機器のこの部分は壊れにくい、この機器は過去に故障したことがあるから要注意など)というのがインタビューの結果であった。それに加えて熟練者は、ダブルチェックをするとか、点検ルートを時々逆順に辿ることによって視点を変えるなど細かな工夫をしていた。
一方で、未熟練者の場合は教わったことをミスなく忠実にトレースする、プラントの正常な状態をできるだけ知るというのが基本的な態度であった。点検ルートや点検箇所の選択の根拠も、OJTで教わったという理由が顕著で、教わった行動以外には考えが及んでいない場合も見受けられた。
つまり、OJTで誰に担当して貰うかによって、未熟練者の点検のやり方や考え方も変わってきてしまう。
マニュアルというのが一つ興味深い観点である。詳細なマニュアルを作って点検ルート、点検作業を標準化すれば良さそうに思うが、「日常業務が忙しくて、詳細なマニュアル作成に至っていない」という、筆者自身も含めてありがちな説明に直面するし、詳細なマニュアルをつくっても、すぐに修正点が出てくるし、改訂し続ける手間に人が割けないという訳である。
このプラントでも、最低限点検しなければいけない箇所については、タブレットを配布して、チェックしたり、メーターを読み取って数値を記入したりするようになっている。その上で、点検の自由度がある。
この連載でも触れたが、以前、アメリカの日系の工場でメンテナンスについての調査を行ったが、アメリカだったら、マニュアルを作成することが第一優先の業務となるであろうし、点検員も、マニュアル通りの点検をするであろう。その上での創意工夫というのは期待できない。この辺りに文化的な違い、日本的なものづくりの特徴が現れているように思う。
この研究について学会発表をしたときに、ある先生が面白いコメントをしてくれた(筆者の記憶の範囲で)。
未熟練者は、点検作業を個々の要素作業に分解、整理して、それぞれを着実にこなすことを目標にしている。いわば、システマティックなアプローチである。
一方で、熟練者は全体観があって、職場全体としてはゆらぎを許容しつつ、全体としてシステムが機能するような仕組みになっているシステミックな考え方になっているのではないかと。
このコメントは説得力があって、納得させられる。とすると、日本的ものづくりのエッセンスをDXするためには(それを良しとするとして)、後者のシステミックなところをDXしなければいけない所が難しいし、この連載の主題の1つであるデジタル・トリプレットがねらうべきところであろう。逆に、前者のシステマティックなところは、タブレットの例を挙げるまでもなく、やればできる。課題はむしろ更新し続ける体制づくりということになろう。
そして教育のポイントも、未熟練者に対して、まずはミスなく、抜け漏れなく、間違った判断をしないようなシステマティックなレベルの基礎教育をした上で、システミックな全体観を持つレベルにどうやって引き上げるか、がミッションとなろう。
前者はすでに教育としてはやられていることであろうが、後者はOJTだったり、徒弟制度であったり、属人的な教育方法しか見出されていないのではないか。まさにこれをシステマティックに教えるためにはどうすれば良いのかが課題である。
課題はおぼろげながら分かったのだが、どうやってデジタル・トリプレットを構築すれば良いか、なかなか難しい興味深い課題である。
この記事は、会員専用記事です。
有料会員になると、会員限定の有料記事もお読みいただけます。





